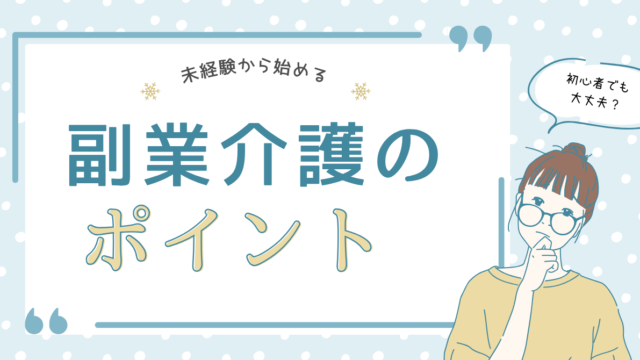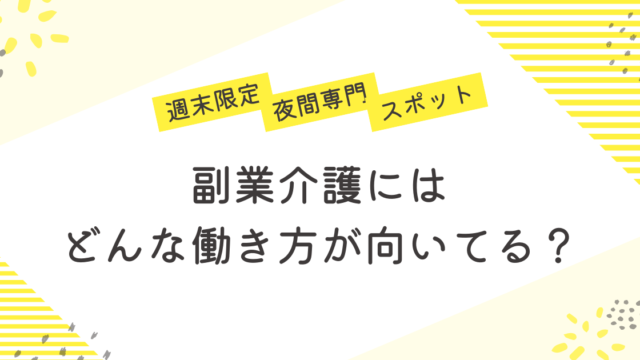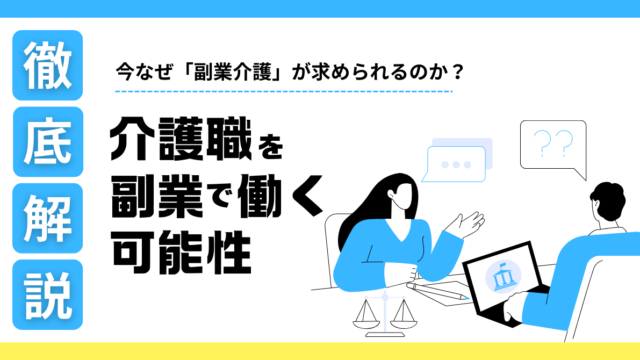「副業解禁」の流れが加速する中、介護職が副業として注目を集めています。
本業があるサラリーマン、専業主婦(主夫)、定年後のシニア層まで、様々な立場の人が「副業介護」にチャレンジしています。実は介護業界は慢性的な人手不足で、副業人材を積極的に受け入れる体制が整っているんです。
この記事では、副業として介護の仕事を始めるメリット・デメリットから、ライフスタイル別の働き方まで、実践的な情報をお届けします。
無理なく長く続けられる「副業介護」のカタチを探していきましょう。
今、副業として介護の仕事が注目される理由

副業というと、フリーランス系の仕事やデリバリー、Webライターなどが思い浮かぶかもしれません。でも最近、「介護のバイト」が副業として人気を集めています。なぜ今、副業として介護が選ばれているのか、その背景を見ていきましょう。
日本の介護人材不足と高まる需要
日本は超高齢社会に突入し、介護サービスの需要は年々拡大し続けています。厚生労働省の推計によると、2025年度には約243万人の介護職員が必要とされていますが、現状のペースでは32万人以上が不足する見込みです。
この人材不足を背景に、介護業界では様々な働き方を受け入れる体制が整備され、「週1日だけ」「夜間のみ」「短時間勤務」など、副業としても働きやすい環境が広がっています。「副業歓迎」の求人も増加中で、求人サイトでは「副業可」の介護職求人が都市部を中心に多数掲載されています。
特に新型コロナウイルスの影響で介護人材の需要はさらに高まっており、業界全体で「未経験者」や「副業者」を積極的に受け入れる傾向が強まっています。
「働き方改革」で広がる副業の可能性
副業解禁の流れは政府の働き方改革とも連動しています。2018年1月、厚生労働省はモデル就業規則から「許可なく他の仕事に従事してはならない」という副業禁止規定を削除。さらに「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、企業に副業容認を促しています。
実際、大手企業を中心に副業を認める動きが広がり、「副業」「兼業」という働き方が一般化してきました。副業を禁止している企業でも、「届出制」に変更したり、一定の条件下で認めるケースが増えています。
この流れを受けて、本業と両立しやすい介護の仕事が「堂々と取り組める副業」として注目されているのです。労働者側も「複数の収入源を持つ」という新しい働き方に関心を持つ人が増えています。
コロナ禍後の収入アップ志向と社会貢献意識
コロナ禍を経て、多くの人が「収入の多角化」に目覚めました。一つの仕事だけに依存するリスクを実感し、副収入を得る重要性が再認識されています。そんな中、比較的安定した需要がある介護職は収入源として魅力的な選択肢となっています。
また、社会貢献への意識も高まっています。特に「人の役に立ちたい」「社会とつながりたい」という思いを持つ人にとって、介護の仕事は大きな充実感を得られる場となっています。単なる「お金を稼ぐ副業」ではなく、「社会参加の機会」としての側面も、介護副業の魅力となっているのです。
副業介護で得られる5つのメリット

副業として介護の仕事を選ぶと、どんなメリットがあるのでしょうか。お金を稼げること以外にも、意外な良さがたくさんあります。
ここでは副業介護の5つの大きなメリットをご紹介します。
未経験でもチャレンジできる
介護業界の最大の特徴は、未経験者を積極的に受け入れる土壌があることです。深刻な人手不足を背景に、「無資格・未経験OK」の求人が多数あります。特に施設介護では、資格がなくてもできる業務が多く、初心者でも働きやすい環境が整っています。
多くの施設では入職後の研修制度が充実しており、基本的な介助技術から学べるため、全くの未経験でも安心してスタートできます。初めは見守りや話し相手、食事の配膳など、比較的簡単な業務から始めて、徐々にスキルアップしていくケースが一般的です。
「他業種での仕事経験」も思いのほか評価されます。例えば接客業の経験者なら利用者との会話術が活かせますし、事務職経験者は記録作成が得意だったりします。全く新しい分野にチャレンジする不安はあるかもしれませんが、これまでの経験が思わぬ形で役立つことが多いのも介護の仕事の特徴です。
自分のペースで働ける
副業の大きな悩みは「本業との両立」ですよね。介護業界では様々な勤務形態があり、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選びやすいのがメリットです。
例えば「登録ヘルパー」なら、自分の都合が良い時間帯だけ勤務することができます。「週1回・夜勤専門」「土日のみ」「平日の夕方2時間だけ」など、施設によっては非常に柔軟なシフト設定が可能です。
特に訪問介護の登録ヘルパーは、フリーランスに近い自由度があります。「月曜と水曜の午前中だけ」「息子の習い事の間だけ」など、空き時間を有効活用できるのは大きな魅力です。子育て中の方や、不規則な本業を持つ方でも、スケジュール調整がしやすい職種と言えるでしょう。
資格取得支援で将来のキャリアにも繋がる
副業として始めた介護の仕事も、資格を取得すれば将来のキャリアに繋がる可能性があります。介護職は働きながらステップアップできる職種で、未経験からでも「介護職員初任者研修」→「実務者研修」→「介護福祉士」→「ケアマネジャー」といったキャリアパスが明確に用意されています。
特筆すべきは、資格取得のための支援制度が充実していること。入門資格である「介護職員初任者研修」は各自治体や国の支援制度で受講料の補助や給付金が用意されており、条件を満たせば無料〜半額程度で取得可能です。
さらに、働き先によっては「資格取得支援制度」を設けているところも多く、勤務しながら資格を取得できるケースもあります。副業として始めたとしても、将来的に転職や独立の可能性が広がるのは大きなメリットと言えるでしょう。
人の役に立つ実感と心の充実感
介護の仕事の醍醐味は、何と言っても「人の役に立っている」という実感を直接得られることです。利用者さんやご家族から「ありがとう」と言われた時の喜びは、お金では買えない価値があります。
特に本業がデスクワークやルーティンワークの方にとって、人と直接関わる介護の仕事は新鮮な刺激となります。「人生の先輩から様々な知恵や経験を教わる機会」と捉えると、単なる副収入以上の価値が見えてきます。
また、介護の現場では利用者さんとの何気ない会話や笑顔が日常的に生まれます。そうした温かい交流が「心の充実感」につながり、副業でありながらも「やりがい」を感じられる職場になるのです。本業のストレス発散や気分転換にもなり、精神的な健康維持にも役立つと言われています。
家族介護にも活かせる知識とスキル
介護の仕事で得た知識やスキルは、将来自分の家族の介護が必要になった時にも必ず役立ちます。実際、「親の介護に備えて」と副業で介護を始める方も少なくありません。
介護の基本技術(移動の介助方法、食事の介助、体位変換など)を学べるだけでなく、介護保険制度の仕組みやサービスの利用方法など、実践的な知識を身につけられます。これは家族の介護が必要になった時、適切なサービスを選んだり、家族を支援したりする際に大いに役立つでしょう。
また、認知症や様々な疾患への理解も深まるため、家族が健康問題を抱えた際にも冷静に対応できるようになります。「人生の学び」として捉えれば、副業介護で得られるものは単なる給料以上の価値があると言えるでしょう。
副業介護で気をつけておくこと

副業として介護を始める場合、メリットばかりでなく現実的な課題もあります。ここでは、あらかじめ知っておきたい注意点と、それを乗り越えるためのポイントをご紹介します。準備しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、長く続けられる副業にすることができます。
体力的・精神的負担の軽減
介護の仕事は想像以上に体力を使います。移動介助や入浴介助など、身体を使った業務が多いため、慣れないうちは疲労が蓄積しがちです。特に本業と掛け持ちする場合は、疲労管理が重要なポイントになります。
体力的な負担を減らすためには、まず「自分の体力と相談した無理のないシフト」を組むことが大切です。例えば、本業で既に疲れている日は副業を入れない、夜勤明けの日に本業が重ならないよう調整するなど、自分の体力と相談したスケジュール管理が必要です。
また、業務内容を選ぶことも一つの方法です。例えば、体力に自信がない方なら、力仕事の少ない「見守り」や「話し相手」「レクリエーション補助」など、身体的負担の少ない業務から始めるとよいでしょう。職場に体力面での不安を正直に伝えることで、適切な業務分担をしてもらえることもあります。
休養もとても重要です。睡眠時間の確保や、定期的な休息日を設けるなど、体調管理を意識してください。疲れを溜め込むと、本業にも影響が出る可能性があります。
本業との両立への時間管理
副業を始める上で最も重要なのが、本業との両立です。特に法的な側面での注意点もあります。まず確認すべきは、本業の就業規則で副業が許可されているかどうか。禁止されている場合は、規則違反となるため注意が必要です。
また、労働基準法上は、本業と副業の「労働時間は通算」されます。つまり、複数の会社で働く場合でも労働時間は合計して1日8時間・週40時間が原則となります。これを超える場合は、時間外労働となり、36協定の締結や残業代の支払いなどの対応が必要です。
実際の両立のコツとしては、まず「副業に充てる時間」を明確に決めておくことです。「週○時間」「○曜日のみ」など、はっきりとした枠を設定し、そこから外れないようにすることが大切です。スケジュール管理アプリなどを活用して、視覚的に時間管理をするのも効果的でしょう。
もし本業で突発的な残業が発生した場合に備えて、副業先には事前に「急な休みや遅刻の可能性がある」ことを伝えておくと安心です。信頼関係を築いておくことで、柔軟な対応をしてもらえる可能性が高まります。
人間関係のストレスを減らす職場選び
新しい職場での人間関係は、誰にとっても不安要素です。特に副業として限られた時間で働く場合、職場になじむ時間も少なくなりがちです。そのため、人間関係のストレスを減らす「職場選び」が重要になります。
良い職場を見つけるポイントは、面接時の対応や雰囲気をしっかりチェックすること。面接担当者の話し方や質問内容、施設見学時のスタッフ同士の関係性などから、職場の雰囲気をある程度判断できます。副業歓迎の姿勢が明確で、シフトの相談にも柔軟に応じてくれる職場は、働きやすい可能性が高いでしょう。
また、実際に働き始めてからの人間関係づくりも大切です。副業者は勤務日数が少ないため、積極的なコミュニケーションを心がけましょう。「報告・連絡・相談」を徹底し、分からないことは素直に質問する姿勢が大切です。
どうしても職場の人間関係になじめない場合は、無理に続けるよりも早めに他の職場を探すことも検討しましょう。副業の魅力は「選択肢の自由度」にあります。自分に合った職場を見つけることが、長く続けるコツです。
ライフスタイル別!あなたに合った副業介護を

副業としての介護の働き方は、ライフスタイルによって大きく変わってきます。
ここでは、主な3つのタイプ別に、具体的な働き方や成功事例をご紹介します。
【会社員】週末だけで月3万円稼ぐ「夜勤スポット」活用法
平日はフルタイムで働いているサラリーマンにとって、副業の時間を確保するのは容易ではありません。そんな方におすすめなのが「夜勤専従」の働き方です。
夜勤バイトは1回の勤務で高収入が期待できるのが特徴です。例えば、金曜の夜に入り、土曜の朝に帰るといった形で、週1回の夜勤だけでも月に3〜4万円程度の収入が得られるケースもあります。深夜手当込みで「1回あたり1.5〜2万円」の報酬が見込める施設も少なくありません。
実際、都市部のショートステイ施設などでは「週末限定・夜勤専門スタッフ」の求人が増えています。「金曜夜〜土曜朝」や「土曜夜〜日曜朝」といった形で、本業に支障が出にくいシフトを組むことができるのです。
夜勤の業務内容は「見守り」が中心で、経験を積むまでは熟練スタッフとペアで担当するケースが多いため、未経験でも比較的始めやすい点もメリットです。体力面での不安がある方は、まずは「月2回」などから始めて、徐々に慣らしていくのがおすすめです。
【子育て主婦(主夫)】「スキマ時間」の上手な使い方
子育て中の主婦(主夫)にとって、副業は「家事や育児の合間のスキマ時間」を活用することがポイントです。介護業界には、そんな短時間勤務のニーズにぴったりの働き方があります。
特におすすめなのが「訪問介護の登録ヘルパー」です。これは、事業所に登録しておき、自分の空いている時間帯だけ仕事を入れる働き方。例えば「子どもが幼稚園に行っている9時〜14時だけ」「下の子が昼寝する間の2時間だけ」といった細切れの時間でも働くことができます。
デイサービス施設での短時間パートも人気です。特に「入浴介助」や「食事介助」などの時間帯に人手が必要なため、その時間だけのピンポイント勤務も可能です。例えば、「10時〜13時の入浴・食事の時間帯」だけ働くことで、お迎えの時間までに帰宅できます。
子育て経験は介護の現場でも大いに活かせます。食事の介助や着替えの手伝いなど、日常の家事や育児で培ったスキルがそのまま仕事に応用できるため、未経験でも始めやすいのが特徴です。
子育て中の方は、働く施設を「自宅から近い場所」「子どもの学校や幼稚園の近く」に選ぶことで、移動時間の短縮も図れます。緊急時の対応(子どもの急な発熱など)について事前に相談しておくことも大切です。
【定年後のシニア世代】生きがいと収入を両立させる働き方
定年退職後のシニア世代にとって、介護の仕事は「セカンドキャリア」として注目されています。実際、介護現場では65歳以上のスタッフがいる事業所は全体の68%以上にものぼります。
シニア世代が介護職で働く最大のメリットは、「利用者と年齢が近い」ことです。特に高齢者施設では、同世代の話題で会話が弾みやすく、利用者との信頼関係を築きやすいという強みがあります。長年の社会経験や人生経験も、対人サービスである介護の仕事では大きな武器になります。
体力面での不安がある方は、直接介助よりも「見守り」「話し相手」「レクリエーション補助」などの業務から始めるのがおすすめです。また、事務作業や送迎、環境整備など、専門性を活かした業務を担当するケースも増えています。
働き方としては、週2〜3日の短時間勤務から始め、徐々に体力と相談しながら増やしていくパターンが一般的です。年金と組み合わせることで、無理なく収入を得られるのも魅力です。
また、介護の知識は自分自身や配偶者の将来の健康管理にも役立ちます。「社会とのつながりを保ちながら、役立つ知識も得られる」という一石二鳥の副業と言えるでしょう。
副業介護で人生を豊かにしよう
副業として介護の仕事を選ぶなら、「続けられる環境づくり」がなにより大切です。本業との両立を図りながら、無理なく長く続けるためのポイントをお伝えします。
まず基本は「自分の限界を知ること」。副業は収入アップが目的であっても、健康を損なっては元も子もありません。無理なシフトで疲労を蓄積させたり、睡眠時間を削ったりすることは避けましょう。特に介護の仕事は想像以上に体力を使います。最初は欲張らず、週1回や月数回から始めて、徐々に自分のペースを掴んでいくことをおすすめします。
また、長く続けるには「スキルアップ」も重要です。介護の入門資格である「介護職員初任者研修」は、自治体の支援制度を利用すれば比較的安価(場合によっては無料)で取得できます。資格があれば時給アップにつながり、より効率的に収入を得られるようになります。
一番大切なのは「介護の仕事を好きになること」。単なる収入源として割り切るのではなく、人との関わりや社会貢献の喜びを感じられると長続きします。利用者さんの笑顔や「ありがとう」の言葉が、あなたの活力源になるはずです。
副業介護は、収入面だけでなく「人生の学び」としても価値があります。ぜひ自分のライフスタイルに合わせた働き方を見つけて、充実した副業ライフを送りましょう。